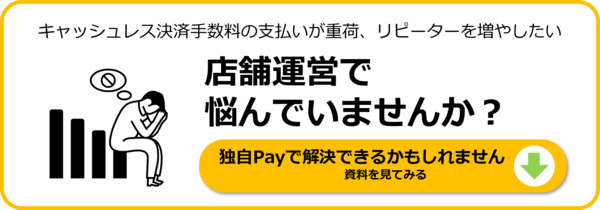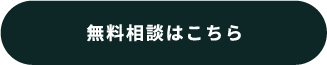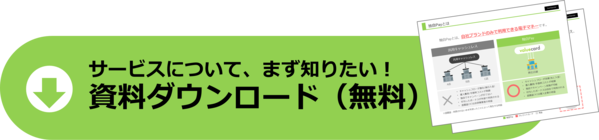小売業における自社アプリケーションの導入メリットや注意点を徹底解説
小売業において、自社アプリの開発を検討する企業が増えています。中堅や大手企業にとどまらず、なぜ今、アプリを採用する企業が拡大しているのでしょうか。
本記事では、小売業でアプリを導入する企業が増えている理由やアプリの導入メリット、注意点などを詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.リテールとは?
- 2.小売業界のアプリに必要な機能
- 2.1.1. 商品情報閲覧機能
- 2.2.2. オンラインショッピング機能
- 2.3.3. ポイントカード機能
- 2.4.4. クーポン配信機能
- 2.5.5. プッシュ通知機能
- 2.6.6. 店舗情報閲覧機能
- 2.7.7. スタッフ紹介機能
- 2.8.8. 口コミ・レビュー機能
- 2.9.9. 決済機能
- 3.小売業界でアプリを導入する企業が増える3つの理由
- 3.1.折込チラシによる宣伝効果の低下
- 3.2.電子チラシサービスの採用
- 3.3.オンラインショップ利用者の増加
- 4.小売業がアプリを導入する5つのメリット
- 4.1. 利便性が増し、より良い買い物体験を提供できる
- 4.2.顧客とのつながりを維持できる
- 4.3.お得情報を提供しやすい
- 4.4.ポイント制度を活用しやすい
- 4.5.キャッシュレス決済に対応できる
- 4.6.顧客データを活用できる
- 5.小売業がアプリを導入する2つのデメリット
- 5.1.開発コストがかかる
- 5.2.アプリのインストールにハードルがある
- 6.小売業がアプリを導入する際に気をつけたい3つの注意点
- 6.1.アプリ導入の目的を明らかにしておく
- 6.2.アプリの運用体制を整えておく
- 6.3.新規顧客の獲得を期待しない
- 7.顧客が増えないアプリの特徴
- 7.1.1. ターゲット顧客層に合致していない
- 7.2.2. アプリの機能や価値が伝わっていない
- 7.3.3. 競合アプリとの差別化ができていない
- 7.4.4. 運用・更新が滞っている
- 7.5.5. 顧客とのコミュニケーションが不足している
- 7.6.6. アプリの目的が不明確
- 7.7.7. 効果測定・分析をしていない
- 8.顧客視点で使いやすいアプリの5つの特徴
- 8.1.操作性が優れている
- 8.2.動作が軽い
- 8.3.顧客ロイヤリティを高める機能を組み込む
- 8.4.目的との親和性が高い
- 8.5.目的達成までの手順が少ない
- 9.まとめ
リテールとは?
リテールとは、一般消費者向けの「小売」を指す言葉です。卸売業(ホールセール)の対義語として使われます。具体的には、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、アパレルショップ、飲食店など、私たちが日常的に利用する多くの店舗がリテール業に該当します。これらの店舗は、生産者や卸売業者から商品を仕入れて、最終消費者に販売することで利益を得ています。
近年では、ECサイトやフリマアプリなどのオンライン販売もリテール業に含まれるようになっています。リテールは、商品を消費者に届ける最後の砦として、重要な役割を担っています。
小売業界のアプリに必要な機能
小売業界のアプリには、顧客満足度向上や業務効率化を実現するために、様々な機能が求められます。以下、代表的な機能と、それぞれがもたらす効果について説明します。
1. 商品情報閲覧機能
商品画像、詳細説明、在庫状況などを閲覧できる機能です。顧客は、アプリで商品情報を確認することで、来店前に必要な情報を収集できます。また、店舗スタッフは、顧客からの商品に関する質問にスムーズに回答することができます。
2. オンラインショッピング機能
アプリ内で商品を購入できる機能です。顧客は、時間や場所を問わずに商品を購入することができ、利便性が向上します。また、店舗側にとっても、新たな販売チャネルを確保することができます。
3. ポイントカード機能
アプリ内でポイントを貯めたり、利用したりできる機能です。顧客は、アプリでポイントを管理することで、ポイントの有効期限を把握しやすくなり、利用意欲を高めることができます。また、店舗側にとっても、顧客の購買履歴を分析し、効果的なマーケティング施策を実行することができます。
4. クーポン配信機能
アプリ限定のクーポンを配信する機能です。顧客は、クーポンを利用することで、お得に商品を購入することができます。また、店舗側にとっても、新規顧客の獲得やリピーターの促進効果が期待できます。
5. プッシュ通知機能
新商品情報やセール情報などを顧客にプッシュ通知する機能です。顧客は、最新情報を逃さずに受け取ることができ、購買意欲を高めることができます。また、店舗側にとっても、タイムリーな情報発信で顧客とのエンゲージメントを強化することができます。
6. 店舗情報閲覧機能
店舗の所在地、営業時間、アクセス方法などを閲覧できる機能です。顧客は、アプリで店舗情報を確認することで、スムーズに店舗を探すことができます。また、店舗側にとっても、顧客への情報発信の場として有効活用することができます。
7. スタッフ紹介機能
店舗スタッフのプロフィールや専門分野を紹介する機能です。顧客は、アプリでスタッフ情報を確認することで、より自分に合った商品やサービスを選ぶことができます。また、店舗側にとっても、スタッフの個性をアピールし、顧客との信頼関係を築くことができます。
8. 口コミ・レビュー機能
顧客が商品やサービスに対する口コミやレビューを投稿できる機能です。顧客は、他のユーザーの意見を参考に、商品やサービスを選ぶことができます。また、店舗側にとっても、顧客満足度を把握し、商品やサービスの改善に役立てることができます。
9. 決済機能
アプリ内で商品やサービスの決済ができる機能です。顧客は、現金を持ち歩かずにスムーズに決済することができます。また、店舗側にとっても、会計処理の効率化や売上データの収集に役立てることができます。
上記のように、小売業界のアプリには、顧客満足度向上や業務効率化を実現するために様々な機能が求められます。これらの機能を効果的に組み合わせることで、顧客ロイヤリティの向上や売上拡大につなげることができます。
なお、アプリ開発を検討する際には、ターゲットとする顧客層やアプリの目的を明確にし、必要な機能を絞り込むことが重要です。
小売業界でアプリを導入する企業が増える3つの理由
小売業でアプリの導入が増えている理由は、大きく3つあり「折込チラシによる宣伝効果の低下」、「電子チラシサービスの採用」、「オンラインショップ利用者の増加」です。スマートフォンの普及によってインターネット利用が一般化した現代では、従来の手法では顧客に効果的な訴求が行えません。
そのため、小売業でもアプリを活用した新しいアプローチが求められています。ここでは、小売業界でアプリの利用が増えている3つの理由について解説します。
折込チラシによる宣伝効果の低下
これまでスーパーなどは、特売の宣伝をするために新聞の折込チラシを活用してきました。
新聞の折込は一定の費用負担はあるものの、宣伝効果が高く、店舗周辺の顧客に効率よく情報を発信するためには欠かせない媒体でした。しかし、新聞の購読率が低下している今、チラシの宣伝効果も下がっています。
特に若い世代を中心に十分な情報訴求が行えないことから、アプリの活用に注目が集まるようになりました。
電子チラシサービスの採用
折込チラシの効果が薄れたことで、電子チラシを活用する企業が増えています。チラシ情報をまとめたサイトなどもありますが、自社アプリであれば、他社のチラシに埋もれることなく、自社のチラシを訴求することができます。
オンラインショップ利用者の増加
オンラインショップの利用者が増加していることも、小売業でアプリの利用が増えている理由の1つです。リモートワークの普及なども後押しし外出頻度が減っている昨今、自宅で完結できるオンラインショップを利用する人が増加傾向にあります。
また、オンラインショップは、実店舗のようにお店に行かないと商品在庫の有無が確認できないといったことがないため、顧客側の負担が少ないと言えるでしょう。
小売業がアプリを導入する5つのメリット
小売業がアプリを導入することで得られるメリットは次の5つです。
- 利便性が増し、より良い買い物体験を提供できる
- 顧客とのつながりを維持できる
- 顧客に対し、お得な情報を提供しやすい
- ポイント制度が活用しやすい
- キャッシュレス決済に対応できる
それぞれの内容について紹介します。
利便性が増し、より良い買い物体験を提供できる
アプリを導入することで、顧客にとっての利便性が増し、より良い買い物を体験いただけるようになります。
買い物体験が向上した例としては、ニトリアプリの「手ぶらdeショッピング機能」が挙げられます。「手ぶらdeショッピング機能」は、店舗で購入したい商品のバーコードを読み取るだけで買い物リストを手軽に作成できる機能です。買い物リストはオンラインショップとも連携でき、「オンラインショップで購入する」「店舗宅配受付で清算して宅配の手配をする」のどちらかが選択できます。
顧客にとっては、店内で商品を運ぶ手間が省けるだけでなく、自宅に運ぶ手間も省くことができます。さらに、その場では購入せず、買い物リストの商品を後からオンラインで購入できる点も、今の時代にマッチした買い物といえるでしょう。
参考:ショートタイムショッピングとOMOを実現 自宅用/店舗用タブで最適な体験を届けるニトリアプリを開発支援
顧客とのつながりを維持できる
アプリのプッシュ通知を活用することで、受動的な顧客へも特売情報などを送ることができます。店舗とのつながりを維持でき、売上向上につなげやすくなるでしょう。
また、アプリであれば会員証やポイントサービス、決済・予約システムなど、情報提供以外の用途でも活用できるため、顧客とのタッチポイントを複数用意できます。
お得情報を提供しやすい
アプリによるプッシュ通知によって、顧客はアプリやWEBサイトを起動しなくても、新製品やクーポン、キャンペーンなどのお得な情報を取得できます。プッシュ通知はリアクション率が高いので、効果的な情報発信が可能です。
WEBベースのホームページでは基本的に情報提供しかできないため、全顧客に同じ情報しか提供ができません。しかし、アプリであれば、顧客の閲覧履歴や購買履歴、年齢、性別などの情報を取得できるため、顧客に合わせた最適な情報を発信できます。
ポイント制度を活用しやすい
デジタルでポイント制度を活用できる点も、アプリの大きなメリットです。ポイントカードをアプリと一体化することで、店舗側はカード発行にかかるコストや手間を削減できます。
キャッシュレス決済に対応できる
アプリにキャッシュレス決済機能を加えることができます。キャッシュレス決済を導入することで、店舗側には客単価の向上や販売機会の増加、レジ業務の効率化といったメリットが生まれるでしょう。
なお、バリューデザインが提供するキャッシュレス決済サービスは「店舗専用の電子マネー」の発行から、ポイント機能や会員管理機能など販促に欠かせない機能を備えたサービスです。
既存顧客の囲い込みによる売り上げ向上やキャッシュフローの改善に課題を感じている方は、お気軽にお問い合わせください。
顧客データを活用できる
アプリを通して顧客の購買履歴や閲覧履歴などのデータを収集・分析することで、顧客のニーズや嗜好を深く理解することができます。そのデータに基づいて、以下のような施策を実行することで、顧客満足度向上と売上向上につなげることができます。
- 個別化された商品提案やクーポン配信:顧客一人ひとりに最適な商品やサービスを提案することで、購買意欲を高めます。
- 効果的なマーケティング施策の実施:顧客の属性や行動データに基づいて、最適なタイミングで最適なチャネルで広告配信を行うことができます。
- 顧客ロイヤリティの向上:顧客とのコミュニケーションを強化し、満足度の高い顧客体験を提供することで、顧客ロイヤリティを高めます。
顧客データを活用することで、より顧客一人ひとりに寄り添ったマーケティング活動が可能となり、競争優位性を築くことができます。
小売業がアプリを導入する2つのデメリット
顧客満足度向上や売上拡大が期待される小売業におけるアプリ導入ですが、一方で見逃せないデメリットもあります。デメリットもしっかりと理解したうえでアプリの導入を検討しましょう。
開発コストがかかる
小売業にとって、アプリ導入は顧客との新たな接点創出や売上拡大のチャンスとなる一方で、大きな開発コストという壁が立ちはだかります。
アプリ開発には、企画・設計、デザイン、開発、テスト、リリース、運用など、様々な工程がかかります。これらの工程をすべて自社で行う場合、数百万から数千万円もの費用が必要となるケースも少なくありません。さらに、アプリをリリース後も、アップデートやメンテナンス、セキュリティ対策などのコストが発生します。これらのランニングコストも考慮すると、長期的な視点で年間数百万~数千万円程度の費用がかかる可能性があります。
中小企業の場合、こうした高額な開発コストは大きな負担となり、アプリ導入を断念せざるを得ないケースも出てきます。また、せっかくアプリを開発しても、十分な機能を搭載できなかったり、デザインが洗練されていなかったりすると、顧客に利用してもらえず、投資が回収できないというリスクもあります。
アプリ開発を成功させるためには、初期費用とランニングコストを事前にしっかりと把握し、予算に合致する計画を立てることが重要です。また、自社で開発を行うのか、外部業者に依頼するのかについても、慎重に検討する必要があります。
近年では、比較的安価にアプリ開発ができるクラウドサービスや、テンプレートを活用した開発方法なども登場しています。これらのサービスをうまく活用することで、開発コストを抑えながら、効果的なアプリを開発することが可能になります。
アプリのインストールにハードルがある
小売業にとって、アプリは顧客との新たな接点となり、売上拡大や顧客満足度向上の可能性を秘めたツールです。しかし、アプリ導入には多くの課題があり、その中でも特に大きな壁となるのが「アプリのインストールハードル」です。
まず、現代社会においてもスマートフォンを持っていない層や、アプリの利用に慣れていない層が存在します。特に高齢者やITリテラシーの低い層にとって、アプリのインストールや設定は煩雑で、大きな負担となる可能性があります。
さらに、近年ではスマートフォンアプリの数は爆発的に増加しており、消費者は限られた時間の中で本当に必要なアプリだけを選び、インストールするようになっています。そのため、小売業者が提供するアプリが、魅力的で差別化されたものでなければ、ユーザーの目に留まらず、インストールしてもらえない可能性が高いです。
アプリをインストールしてもらえなければ、せっかくの機能も意味を成しません。せっかく導入したアプリが利用されなければ、投資した費用や開発労力が無駄になってしまうだけでなく、顧客満足度を下げてしまう可能性すらあります。
小売業がアプリ導入を成功させるためには、ターゲットとなる顧客層を明確に意識し、本当に必要とされる機能を搭載した、魅力的なアプリを開発することが重要です。また、アプリのインストールを促すための効果的なマーケティング施策も必要となります。
アプリは強力なツールとなり得ますが、決して万能ではありません。導入前に十分な検討を行い、課題を克服することが、小売業におけるアプリ活用の成功への鍵となるでしょう。
小売業がアプリを導入する際に気をつけたい3つの注意点
小売業がアプリを導入する際には、以下3点に注意が必要です。
- アプリ導入の目的を明らかにしておく
- アプリの運用体制を整えておく
- 新規顧客の獲得を期待しない
アプリ導入の目的を明らかにしておく
アプリを導入する際は、導入目的を明確にしておくことが大切です。導入目的を明確にしておかないと、期待通りの結果を得ることが難しくなってしまうからです。
例えば、販路を拡大したい場合は「オンラインショップ機能」、顧客満足度を高めたい場合には「ポイント機能」や「クーポン機能」など、課題や目的によって必要な機能が異なります。最大の効果を得るためには、どのような目的を実現したいのかを明確にし、最適な機能を備えたアプリを導入することが不可欠です。
アプリの運用体制を整えておく
アプリを導入する際には、保守・運用体制の構築が欠かせません。
例えば、iOSやAndroidのバージョンアップを受けて、自社のアプリに不具合が生じないかなど、定期的なチェックが必要になります。また、顧客ニーズにあわせて、UIの改修や機能追加などのアップデートもおこなわなければなりません。
これらを適宜実施し、ユーザビリティを向上するために、アプリの保守・運用体制を整えておくことは大変重要です。
新規顧客の獲得を期待しない
アプリを導入しても、アプリによって新規顧客の獲得ができるとは限りません。アプリをインストールしてくれるのは、会員登録をしてくれた顧客やリピーターになっている顧客などがメインです。
よって、アプリ導入の目的を新規顧客獲得にすることはおすすめできません。新規顧客の獲得を目指すのであれば、WEBサイトやネット広告などをメインに利用したほうがよいでしょう。
顧客が増えないアプリの特徴
小売業界において、アプリ導入は顧客との接点拡大や売上向上のための有効な手段として注目されています。しかし、せっかくアプリを開発・導入しても、顧客を獲得できずに成果が出ないケースも少なくありません。顧客が増えないアプリには、以下のような共通点が見られます。
1. ターゲット顧客層に合致していない
アプリの機能やデザインが、ターゲット顧客層のニーズや嗜好に合致していない場合、顧客はアプリを魅力的に感じず、利用を敬遠してしまう可能性があります。
例えば、高齢者向けのアプリで複雑な操作が必要だったり、若い世代向けのアプリで流行を取り入れていない場合などは、ターゲット顧客層を獲得することは難しいでしょう。
2. アプリの機能や価値が伝わっていない
アプリの機能や価値が顧客に十分に伝わっていない場合も、顧客獲得は困難となります。
アプリストアの説明文やアプリ内での案内が不十分だったり、ターゲット顧客層にとって魅力的な機能が備わっていない場合などは、アプリの良さを理解してもらうことができず、ダウンロードや利用に繋がらなくなってしまいます。
3. 競合アプリとの差別化ができていない
類似の機能を持つ競合アプリが多数存在する場合、自社のアプリが埋もれてしまい、顧客の目に留まらない可能性があります。
競合アプリと比較して、どのような点が優れているのか、どのような独自機能があるのかを明確に打ち出し、顧客に訴求することが重要です。
4. 運用・更新が滞っている
アプリをリリースしたら終わりではなく、継続的な運用と更新が必要です。
新商品情報やキャンペーン情報の更新、不具合の修正などを行わないアプリは、顧客にとって魅力を失い、利用しなくなってしまう可能性があります。
5. 顧客とのコミュニケーションが不足している
アプリを通して顧客とコミュニケーションを図ることで、顧客満足度向上やエンゲージメント強化に繋げることができます。しかし、一方的な情報発信のみで、顧客からの意見や要望に耳を傾けないアプリは、顧客との信頼関係を築くことができず、離脱を招いてしまう可能性があります。
6. アプリの目的が不明確
アプリを導入する目的が明確でない場合、アプリ開発の方向性や機能選定がブレてしまい、顧客にとって魅力的なアプリとなることが難しいです。売上向上なのか、顧客満足度向上なのか、顧客とのコミュニケーション強化なのか、アプリの目的を明確にし、それに沿った機能やデザインを開発することが重要です。
7. 効果測定・分析をしていない
アプリの利用状況や顧客の反応を分析することで、アプリの改善点や課題を発見することができます。しかし、効果測定・分析を行わないままでは、アプリが顧客にとって本当に有効なのかどうかを判断することができず、改善の機会を逃してしまう可能性があります。
顧客を増やし、アプリを成功させるためには、これらの特徴を踏まえ、ターゲット顧客層に合致した魅力的なアプリを開発し、継続的な運用と改善を行うことが重要です。顧客とのコミュニケーションを重視し、アプリを通して顧客満足度向上に繋げる努力も必要です。
顧客視点で使いやすいアプリの5つの特徴
顧客の利便性を無視したアプリを開発してしまうと、利用者数は伸びず、導入目的も達成できません。継続的に顧客にアプリを利用してもらうために必要な5つの特徴についてご紹介します。
操作性が優れている
顧客視点で使いやすいアプリを作るためには、操作性を重視しなければなりません。ソフトウェアや関連サービスを提供する「ジャストシステム」が、アプリをアンインストールする理由を調査したところ、削除理由の2位に「実際に操作してみたときに操作しにくかったとき」がランクインしました。
買い物体験を向上させるための機能も大切ですが、それ以上にユーザビリティの高いアプリを開発することが重要です。
参考:6割以上は「3ヶ月以上未使用」なアプリを削除対象に【ジャストシステム調査】
動作が軽い
アプリの起動が早いなど、動作が軽いことも使いやすいアプリには欠かせない要素です。前述の調査では「起動に時間がかかったとき」が、アプリを削除する理由の4位にランクインしています。
動作が重いと会計時の会員証提示などにも時間がかかり、顧客だけでなく店舗スタッフもわずらわしさを感じてしまうことでしょう。アプリを開発する際には、すべての機能がサクサク動くことも大切な評価指標です。
顧客ロイヤリティを高める機能を組み込む
顧客が使えば使うほどお得になる機能を組み込むことで、顧客ロイヤリティの向上が期待できます。小売店のアプリであれば、会員証やポイントカード、クーポンといった機能を組み込むことで、利用促進および収益向上につなげられるでしょう。
例えば、PLAZAの会員サービスアプリ「PLAZA PASS」では、会員証やポイント、購入回数に応じたステージ表示など、さまざまな機能を組みこむことで顧客ロイヤリティを高める工夫をしています。
目的との親和性が高い
使いやすいアプリを開発するためには、目的との親和性も高めなければなりません。
アプリの導入によってどのような目的達成や課題解決をしたいか明確にし、それらを実現できる機能やサービスを実装することが求められます。また、顧客の目的にマッチしたUI・UXの設計も重要なポイントです。
目的達成までの手順が少ない
顧客の目的達成までの手順を少なくすることも大切です。
例えば、オンラインショップ機能が備わったアプリの場合、カートに入れてから購入完了までの手順が多いと、購入手続き中の離脱を招くおそれがあります。最悪の場合、アプリを削除されて二度と使われない可能性もあるでしょう。
操作ステップや入力回数などを減らして、目標達成までの手順を少なくすることが、使いやすいアプリを開発するためのコツです。
まとめ
小売業の収益拡大や顧客ロイヤリティ向上のためには、アプリの導入は有効と言えるでしょう。ただし、アプリを開発する場合、ゼロから構築するとなると膨大な費用がかかってしまいます。開発時間やコスト面での負担を押さえるなら、パッケージ化されたアプリを導入するのも良いでしょう。
既存ソリューションの有効活用も視野に入れて、効率よく導入する方法を検討してみてはいかがでしょうか。なお、キャッシュレス決済サービスを連携させたい場合は、以下のお問い合わせよりお気軽にご相談ください。